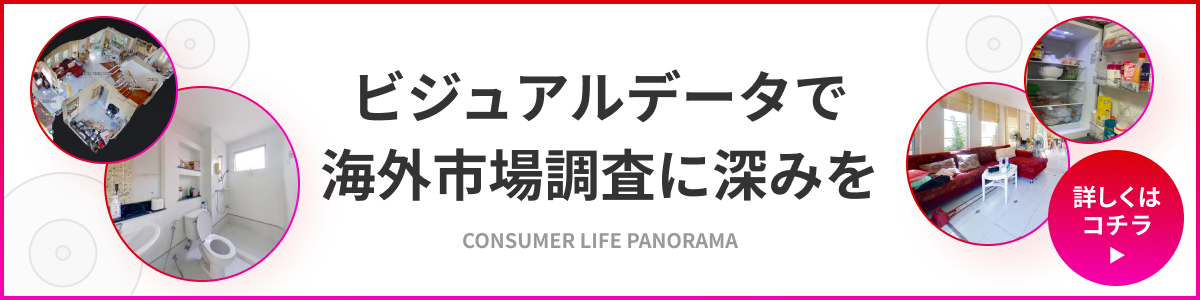【中国:地球の暮らし方】中国人は水よりお湯を好む理由
- 公開日:2023/08/22
- 13977 Views
水は命の源という言葉のように、水分の補給は人間にとって毎日必要不可欠なことである。ベトナムでの水へのこだわり(【ベトナム:地球の暮らし方】 ベトナム人の水質へのこだわり(https://www.global-market-surfer.com/pickup/detail/385/))については以前ご紹介したが、今回は、水だけでなく、「飲み物」というキーワードで、ベトナムに文化の近い中国人生活者の飲み物の習慣について、Consumer Life Panoramaに登録されている中国の生活者をご紹介しながら、解説していきたい。
「失礼だから」だけではない、水ではなくお湯をお客に出す理由
日本と中国の両方で生活したことのある方なら、レストランに行ったときの日本と中国の一つの違いに気づくだろう。それは、日本の場合、「お冷」という氷入りの水を出すのが一般的であるのに対し、中国では「お冷」どころか、普通の水もあまり出さずに、その代わりに熱いお茶が出されていることだ。
日本や欧米諸国では、水やお冷を飲む習慣があるのに対して、中国では、レストランでお冷が出されたら、お客は失礼だと思うに違いない。それはレストランに限ったことではなく、友達が来た時にも、温かいお茶で招待することが多い。お茶がない場合は、少なくとも温めた水やお湯は用意しておく必要がある。それは、自分の温かい気持ちを表す方法でもあるのだ。
実は中国では、お冷や常温の水ではなくお湯を出す理由は、失礼だからというだけではない。その理由は中国の独特な伝統と歴史にある。伝統面の話は、以前「小物編」(https://www.global-market-surfer.com/pickup/detail/168)でも紹介したように、その裏には、中医の陰陽調和という理論がある。お湯を飲むと、「温陽」という効果があり、寒さを追い払い、体の中の「陰」の気を中和することで、病気を治す効果があると中国人は昔から信じている。
また、歴史的な面でいうと、数千年前からお湯でお茶を淹れて飲む習慣があるのに加え、特に1950年代からの不衛生な生水による伝染病の広がりで、政府は何か対策を打つ必要があった。ヨーロッパ諸国や日本の場合は、基本的に上下水道の改造などで蛇口から出る水の水質を直接飲めるレベルに改善する方法を取ったが、それだけの資金がなかった中国では、政府からトップダウンで沸かした水を飲もうという全国的な運動が始まり、その習慣が今でも伝わる。
2022年年末ごろ、日本ではコンビニで期間限定で販売されている「白湯」が一時的にネットで話題となったが、「白湯」が人気の理由として、女性の冬の寒さ対策や、体によさそうだからなどがあり、健康を意識して飲用する方が多いとのことだが、これは中国でお湯を飲む理由とある程度共通しているかもしれない。
なお、日本では水道水を飲むのは普通だが、中国人は基本的に水道水は飲まない。ベトナム人と同じように、一度沸かして飲むか、市販のミネラルウォーターを買って飲むことが多い。(【ベトナム:地球の暮らし方】 ベトナム人の水質へのこだわり(https://www.global-market-surfer.com/pickup/detail/385/))そのため、中国の家には、ケトルやウォーターサーバーがよく見られる。
温かい飲み物の様々な飲用シーンと器具
冷たい飲み物より、温かい飲み物を中国人が好む理由についてご紹介したが、飲み物によってそれぞれの飲用シーンがある。
最も日常的に、普遍的に飲まれているのはお茶だが、中国では、緑茶、紅茶だけではなく、花茶などもかなり人気。それは伝統だけではなく、健康意識もある。例えば菊は熱を取る効果があり、バラは美容の効果があるといわれている。さらに家庭によっては、花茶やお茶専用のポットまで用意しているのだ。

お茶専用のポットが用意されている家庭(CN_107)
出典:Consumer Life Panorama
Consumer Life Panoramaとは
世界18カ国1,000名以上の生活者のビジュアルデータを蓄積した、ウェブサイト型データベース。住環境を閲覧できる3Dモデルや、各生活者の保有アイテムを撮影した2Dデータが多く搭載されており、文字や数字だけでは把握しづらい海外生活者の理解に役立つ。
本コラムで引用したようなビジュアルデータを用いて、
・海外生活者の属性別の違いを比較する
・カテゴリーの使用実態をリアルに把握する
・ターゲット生活者のライフスタイル全体を理解する
等、「現地に行かない」ホームビジット調査として活用が可能。

一方で、ペットボトル入りのお茶も販売されているが、日本と違い、緑茶でも砂糖入りが多く、日本人の口にはなかなか合わない。その理由は2つあり、一つは品質の悪い茶葉の渋みや苦みを中和するため、もう一つは若年層も含めて、より万人受けの味にするためだ。ただ、近年は健康意識が広がる中で、無糖、ゼロカロリーを提唱する飲料も広がりはじめている。
また、漢方の視点で、補血のために、お湯に黒糖、サンザシ、ナツメなどを入れて月経の時に飲むのが中国人女性の習慣である。そもそも、漢方薬は冷やして飲むものがなく、基本的に、煎じて飲むことが多い。
お湯を沸かす器具はケトルや電気ポットなどがある。保存の器具として、魔法瓶は広く使われている。日本でいう魔法瓶は、保温と保冷の2つの使い道があるが、中国ではよく「保温瓶」と呼んでいることから、基本は保温しか使わないことが読み取れるだろう。
中国では、昔ながらのレトロ保温瓶をいまだに使う家庭もいれば、保温機能のある電気ポットやお湯が出るウォーターサーバーを使う家庭もいる。ところが、いずれも、家に置いて使うのは問題がないが、持ち歩きづらいという欠点がある。そのため、ステンレス製の持ち歩ける水筒のニーズが高い。中でも日本ブランドの魔法瓶は人気が高く、 保温効果が高く評価されている。
水筒を使うシーンはいろいろある。オフィスワーカー の場合は職場でお湯を飲んだり、お茶を淹れたりするために使われている。特に一時期はやっていたのは、長時間の仕事の目の疲れを取るために、目にいいクコの実をお湯の入った水筒に入れるという使い方だ。また、運転、旅行など外出中の水補給にも使われている。さらに、一本寝室に置くと、夜起きてお湯を飲みたいときにもわざわざ寝室から出る必要もなくなる。

水筒、保温瓶とティーポットを持つ家庭(CN_82)
出典:Consumer Life Panorama
-

執筆者プロフィール
ヤン・イェン
日本在住の中国人リサーチャー、中国をメインに海外消費者生活実態を発信。家には3本の水筒を持っている。
-

編集者プロフィール
高浜 理沙
Global Market Surferのサイトづくりを担当。中国出身の同僚の「夏でも冷たいものは飲まない」というポリシーに影響されて在宅勤務時は夏でもお湯か温かいお茶を飲みはじめ、なんとなく冬場の末端冷え性が解消されたような気がしている。
 Global Market Surfer
Global Market Surfer CLP
CLP