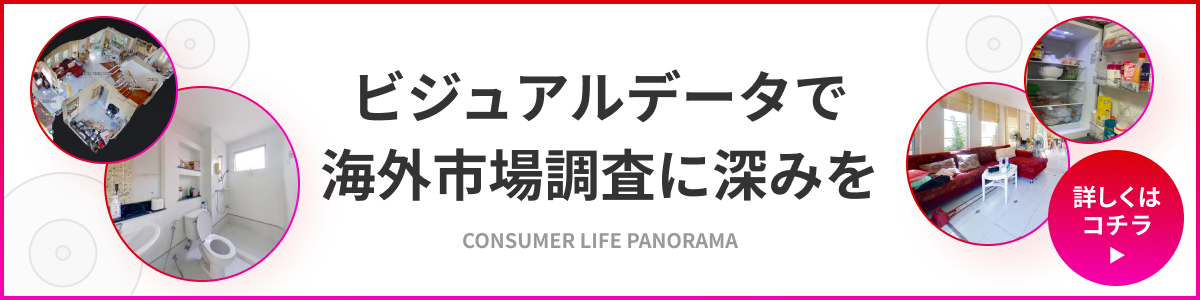【インド】 インドの若者が熱狂!アニメイベントを通して見る意識の変化と課題
- 公開日:2025/09/29
- 更新日:2025/09/29
- 1873 Views
1.「Mela! Mela! Anime Japan!!」の概要
2025年9月13日(土)・14日(日)、インド・ニューデリーで 「Mela! Mela! Anime Japan!! 2025(以下、MMAJ)」 が開催された。本イベントは日印両政府の公認を受け、2024年から始まった日本のアニメと文化を紹介する大規模な催しである。
筆者は昨年に続き、今年も会場を訪れた。目的は、日本イベントの盛り上がりを肌で感じ、日本コンテンツの可能性を考察するためである。
また、近年インドにおいて日本アニメの人気が急速に高まっていることを生活の中で実感しており、その実感が確かなものかどうかを確認する意図もあった。本コラムでは、昨年と今年のMMAJへの参加を通じて、日本イベントの様子や盛況の背景、そして今後の展望についてレポートする。
2.会場の盛り上がり
会場に到着してまず感じたのは、来場者の多さと熱気である。入場無料のためチケットはなく、代わりに紙のリストバンドを受け取って入場するが、その受け取りのために長蛇の列ができていた。

会場入り口の様子(会場はショッピングモールの広場で行われた)
来場者は10代~20代が中心で、男性だけでなく女性も目立った。『NARUTO -ナルト-』や『呪術廻戦』、『ONE PIECE』など週刊少年ジャンプに掲載されているアニメが人気のインドで、これほど多くの女性ファンが参加していたのは筆者にとって意外であった。また、2日間会場にいたIntageインドの同僚によると、初日の土曜日は学生や友人同士、2日目の日曜日は家族連れが多かったという。つまり本イベントは、若年層が男女問わず、友人や家族とともに楽しむ場になっていた。
昨年は2日間で約5万人を集めたが、2025年の来場者数は9月25日時点でまだ発表されていない。しかし、体感としては今年の方がさらに人が多かったように思う。
注目すべきは、40を超える日本企業・団体が参加し、その約半数が日本のIPホルダー(知的財産保有の企業や個人)だった点である。会場の至る所で日本アニメのキャラクターやIPが展開され、ブースやフォトスポットには大勢のアニメファンが集まっていた。

9月14日(2日目)15時頃の会場の様子

ステージではライブやコスプレイベント等が開催された

フォトスポットの様子

『鬼滅の刃』の無限城をイメージした動画配信プラットフォーム「Crunchyroll」のブース
3.インドにおける日本アニメ人気の背景
MMAJをはじめとする、インドにおける日本イベントの集客を支える最大の要因は、間違いなく「日本アニメの人気」である。イベント公式YouTubeでもアニメフェスとしての側面を前面に打ち出しており、MMAJに関連するInstagramの投稿を見てもアニメ関連が多数を占める。
“Mela! Mela! Anime Japan!! 2025” 25-sec CM
インドにおける日本アニメの人気は、新型コロナ禍以降に急速に拡大した。NetflixやYouTubeなどの配信プラットフォームを通じ、10代~20代の若者を中心に日本コンテンツが日常に浸透している。若者に話を聞くと、コロナ禍以降は「友達との会話で話題になる」「兄弟や親戚が見ている」ことをきっかけに視聴を始めるケースが多いという。口コミの影響力が大きいインドでは、話題化した作品が急速に広まる傾向がある。
事実、イベント前日に公開された『鬼滅の刃 無限城編』は、前売り売上がインドにおけるハリウッド映画以外の外国映画として最高を記録した。ヒンディー語吹替版の4DX上映では動員率100%を達成し、需要が供給を上回る盛況ぶりだったという。2020年公開の『鬼滅の刃 無限列車編』がインドではほとんど上映されなかったことを考えると、日本アニメの人気がインドでいかに急速に高まったかが分かる。
2000年代初頭から放送されていた『ドラえもん』や『クレヨンしんちゃん』は、長年子どもたちに人気だった。しかし、コロナ禍以前は『NARUTO -ナルト-』や『DEATH NOTE』といった作品も「子どもが見るもの」と捉えられていた。筆者が赴任した2022年当時も、まだ「アニメ=子ども向け」と考える人が多かった印象がある。当時に実際、インドの食品会社の方にインタビューした際も、アニメのキャラクターをパッケージに採用するとしたら、子ども向け商品の場合のみと語っていた。
ところが今では『鬼滅の刃』 『呪術廻戦』などを中心に、若者の意識は大きく変化しつつある。実際に筆者の同僚からは「アニメ=オタク」というイメージはなく、(週刊少年ジャンプに掲載された漫画の)アニメは「かっこいいもの」と捉えられていると聞いた。日本アニメのIPが企業とコラボして商品を販売していたり、映画館で毎月のように日本のアニメ映画が公開されていたりと、日本アニメの環境は驚くほど変化している。日本アニメがインドの若者に浸透したことが、日本文化やイベント来場の大きな原動力となっていることは疑いない。
4.日本アニメの展望と課題
日本アニメには今後さらなる拡大の余地がある。しかし今後の課題は「言語」と「収益化」であると筆者は考える。
まず言語面では、インドは地域ごとに異なるローカル言語が存在する。都市部でも映画を観る際に英語字幕より、ヒンディー語など馴染みのあるローカル言語の吹替を望む人が多い。実際、筆者の友人(20歳の大学生)は「子どもの頃からタミル語吹替で『クレヨンしんちゃん』を見てきたので、新作映画もタミル語でしか考えられない」と話していた。日本人にとって「しんちゃんの声」といえば特定の声が思い浮かぶのと同じように、インドでもキャラクターに「この声」という定着したイメージがあるようだ。現在、インドでテレビ放送があったアニメ以外の、多くのアニメは英語字幕版しかなく、言語面でのアクセスが限定的である。グッズやイベント展開を視野に入れるなら、ターゲットを誰にし、どの言語に対応するかを戦略的に考える必要がある。

ヒンディー語、タミル語、テルグ語吹き替えでの公開が決まった『クレヨンしんちゃん』の新作映画
(バンガロールの映画館にて筆者撮影)
次に収益化の課題がある。インドでは漫画文化が根付いておらず、日本漫画の輸入版は1冊1,000円以上と高額で若者に手が届きにくい。そのため多くの人にとって日本アニメの入り口は動画配信だが、多くが無料の海賊版サイトや、家族・親戚の動画プラットフォームアカウントを利用した視聴に依存している。つまり「アニメ=無料で見られるもの」という意識が強い。映画館の上映を撮影してSNSに投稿する人も多く、街には正規品ではないであろうアニメグッズやTシャツが売買されており、アニメが著作物であるとの意識も薄い。
日本で数十年かけて醸成されたアニメ文化とは異なり、インドでは数年で急速に広まったため、アニメに対する規範意識やビジネスモデルがまだ確立されていない。企業にとってはIP活用や収益化の方法を見極めることが重要だ。今回のMMAJはIPの正規品の紹介・販売はもちろん、二次転売なども厳格に管理したイベントだったという。こうした日本イベントを通して、日本が醸成してきた文化や意識を広めていくことは大変意義があると考えている。
筆者も日本アニメの一ファンとして、インドでの日本イベントやアニメ人気の広がりは非常に喜ばしい。まだまだ成長とビジネスチャンスを秘めていると信じている。筆者を含め、現地在住のリサーチャーも、エンタメ情報の発信や調査提案を通じて、今後も日本企業やアニメ文化の成長に貢献していきたい。
〈出典〉
Mela! Mela! Anime Japan!!2025 :
https://mmaj.jp/
Pinkvilla, Demon Slayer Infinity Castle Set to Storm Indian Box Office With Historic Advance:
https://www.pinkvilla.com/entertainment/box-office/demon-slayer-infinity-castle-smashes-advance-booking-records-amazes-with-rs-15-crore-pre-sales-already-1396620
etvbharat, Demon Slayer Infinity Castle Smashes Indian Box Office, Scores A CinemaScore, But Can It Surpass Mugen Train Globally?:
https://www.etvbharat.com/en/!entertainment/infinity-castle-smashes-indian-box-office-scores-a-cinemascore-but-can-it-surpass-mugen-train-globally-enn25091307707
-

執筆者プロフィール
赤塩 健太
インド・バンガロール在住の日本人リサーチャー。7年間の小学校教諭からリサーチ業界へ転身。主に食品や飲料などのFMCG案件を担当。近年増加傾向にあるエンタメ関連の案件への理解を深めるため、バンガロールで開催されるアニメやゲームイベントには可能な限り足を運び、全参加を目指している。
-

編集者プロフィール
チュウ フォンタット
日本在住14年目マレーシア人リサーチャー。Global Market Surferのサイト作りを担当。
 Global Market Surfer
Global Market Surfer CLP
CLP