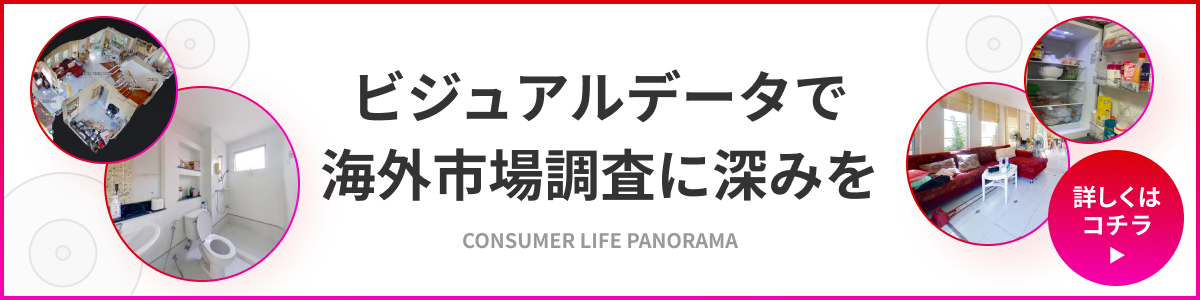【中国:地球の暮らし方】空間最大限利用のためのバルコニー活用術とは?
- 公開日:2020/11/26
- 更新日:2025/09/05
- 15766 Views
中国の暮らしを詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご確認ください。
2025年版|中国のリアルな暮らしとは?押さえるべき日常生活習慣と今のトレンド
・都市部の住宅事情:意外と広くない?間取りと特徴
・空間を最大限に活用する工夫
・リビングに冷蔵庫が置いてある?そして玄関についても日本と考え方が違う
・室内空気室にこだわる中国生活者
など

バルコニーは私有部分に開放的でもない?
中国生活者は室内空間利用のために、バルコニーを最大限に活用する前提がまずある。実は、中国の大半のバルコニーは日本と違って、窓に囲まれている室内空間でもあるのである。 マンションタイプの場合、日本では、バルコニーが共有部分であることは一般的な常識で、基本的には窓がない開放的な空間として造られている。共用部分であるがゆえに、居住面積としては計算されていなく、バルコニーの勝手な改造も禁止されている。バルコニーは物干しとエアコンの室外機の置き場として使われるのが普通で、それ以外には、避難はしごも設置されていて、非常な事態が発生するときに、バルコニーを通って下まで避難できるようなデザインになっている。そのため、バルコニーには容易に動かせないものを置いていけないとか、避難はしごをふさがるような荷物を置いてはいけないとかのようなルールも日本人に一般的に受け入れられている。 一方で、中国では状況が全然違う。中国では、バルコニーが共用部分ではなく、私有部分として、居住面積にも計算されている。そのため、どのように使うかは持ち主の自由である。また、バルコニーの様式はほとんどが日本のように開放的な空間ではなく、室内空間になっている。
日本(左)と中国(右)マンションの典型的なバルコニー
(出典:生活者データベース(Consumer Life Panorama))
Consumer Life Panoramaとは
世界18カ国1,000名以上の生活者のビジュアルデータを蓄積した、ウェブサイト型データベース。住環境を閲覧できる3Dモデルや、各生活者の保有アイテムを撮影した2Dデータが多く搭載されており、文字や数字だけでは把握しづらい海外生活者の理解に役立つ。
本コラムで引用したようなビジュアルデータを用いて、
・海外生活者の属性別の違いを比較する
・カテゴリーの使用実態をリアルに把握する
・ターゲット生活者のライフスタイル全体を理解する
等、「現地に行かない」ホームビジット調査として活用が可能。

実際、インテージのConsumer Life PanoramaにMy Homeが登録されている中国の家庭を見てみると、9世帯のうち、5世帯がバルコニー付きの世帯で、この5世帯全員室内のバルコニーとなっている。(2020年11月集計)
それでは、一体なぜ中国家庭が室内バルコニーにこだわるのだろうか?実は、その根底には、日中の間のバルコニーにかかわる法規上の違いがあるのだ。
一方で、中国において、バルコニーの算入方法が記載されている「建築工程建築面積計算規範」(以下「規範」と略す)は2014年に一回見直しが入ったが、2014年以前の旧「規範」によると、バルコニーが室外にあろうが、室内にあろうが、多くの場合(建築主体の外にバルコニーがある場合)、実面積の1/2で建築面積に加算すると記載されている。
そのため、2014年以前に建築された住居は、バルコニーを室内空間にすることで、紙面上の面積よりもちょっと広めの室内空間を提供することができる。同時に、住宅の買い手からすると、バルコニーの半分の面積はただでもらえるようなお得感がある。中国都市部1人当たり住宅建築面積が決して広いとは言えないため、バルコニーを室内空間にすると、利用できる空間が増え、使い勝手が良いので、生活者にとってもメリットがある。 ちなみに、室内空間のバルコニーに関しては、2014年の新「規範」では1/2面積から全面積に修正されたものの、2014年までに旧「規範」通りに造られたマンションの建築数が多いため、バルコニーが室内にある住居が多く残っている。開放的でないうえに改造も可能?
日本では、新築マンションは内装付きのまま引き渡し、買い手はそのまま入居可能であるのに対し、中国ではマンションは完成前に販売し、内装がないまま引き渡すのが一般的。そのため、入手したらすぐに住めるわけではなく、内装、ないし構造の改造も可能となる。実際には、バルコニーの位置によってほかの空間とつなげる形で改造する家庭も少なくないが、多くの場合、以下の2パターンが多くみられる。

寝室と一体化し、洗濯機のあるバルコニー
(出典:生活者データベース(Consumer Life Panorama))

外壁につける室外機 (出典:生活者データベース(Consumer Life Panorama))
-

執筆者プロフィール
ヤン イェン
日本在住の中国人リサーチャー、中国をメインに海外消費者生活実態を発信。実家ではバルコニーに洗濯機が設置されていて、洗濯と物干しが同じ空間で楽だと感じる。
-

編集者プロフィール
辰田 悠輔(たつだ ゆうすけ)
Global Market Surferのサイトづくりを担当。バルコニーで家庭菜園する友人宅を訪問し、コロナ禍での家庭菜園への憧れが膨らみ始める。
 Global Market Surfer
Global Market Surfer CLP
CLP